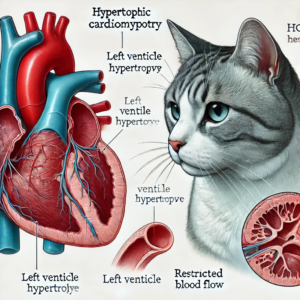犬の僧帽弁閉鎖不全症(MMVD: Myxomatous Mitral Valve Disease)は、高齢の小型犬を中心に多くみられる心臓病です。
心臓には4つの部屋(左心房・左心室・右心房・右心室)があり、それぞれの部屋の間には血液の流れを調整する「弁」が存在します。その中でも、左心房と左心室の間にある弁を「僧帽弁」と呼びます。
通常、僧帽弁はしっかり閉じて血液の逆流を防いでいます。
しかし、MMVDでは僧帽弁が変性し、ピロピロした状態になってしまいます。
弁がうまく閉じられなくなるため、心臓の拍動ごとに左心室から左心房へ血液が逆流してしまいます。
これが進行すると、心臓に負担がかかり、やがて心不全を引き起こすことがあります。
MMVDの主な原因は、僧帽弁の「粘液腫様変性」(Myxomatous Degeneration)です。
僧帽弁の「粘液腫様変性(Myxomatous Degeneration)」とは?
• 僧帽弁の組織が異常に柔らかくなり、弁が厚くなる変化を指します。
• 正常な弁は弾力があり、しっかりと閉じることができますが、粘液腫様変性が進むと、弁が膨らんでしまい、閉じる力が弱まり、血液が逆流するようになります。
• この変性は加齢とともに進行しやすく、特に小型犬(キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、マルチーズ、チワワ、ミニチュア・シュナウザーなど)で多くみられます。
MMVDの進行と症状
MMVDは進行性の疾患であり、早期には無症状のことが多いですが、進行すると以下のような症状が見られることがあります。
✅ 初期(無症状)
• 健康診断で心雑音が指摘されるが、犬自身には特に異常はない。
✅ 中期(軽度~中等度の心不全)
• 運動を嫌がる(疲れやすい)
• 咳が増える(特に夜間や興奮時)
• 呼吸が速くなる
✅ 後期(重度の心不全)
• 重度の呼吸困難(肺水腫)
• 失神することがある
• 食欲不振・体重減少
まとめ
僧帽弁閉鎖不全症(MMVD)は、僧帽弁の粘液腫様変性によって弁が変形し、血液が逆流することで心臓に負担がかかる病気です。
早期の発見と治療が重要であり、心エコー検査やX線検査で進行度を評価し、適切な治療を行うことがワンちゃんの健康を守る鍵となります。
気になる症状があれば、早めに獣医師にご相談ください!
ACVIM(米国獣医内科学会)のガイドラインでは、MMVDの診断と進行度の評価にいくつかの重要な指標が使われます。
ここでは、診断に用いられる主要な数値について、飼い主様にも分かりやすくご説明します。
MMVDの診断に用いられる指標
MMVDの進行を評価するために、左心房が大きくなっていないか、左心室が大きくなっていないか、心臓全体が大きくなっていないか。が重要な指標になります。
1. LA/Ao(左心房/大動脈比)(Left Atrium to Aortic Root Ratio)
何を表す?
大動脈は強くて太い血管のため、そう簡単には大きさは変わりません。
しかし、左心房は弁の隙間から血液が逆流することによって大きくなってしまいます。
一般論として大きくなると良いイメージがありますが、
ゴムを伸ばしたような状態になるため大きさが大きくなると収縮する力は弱まってしまいます。
LA/Ao は、左心房が大きくなっていないかを調べる指標です。
つまりLA/AOが高いということはMMVDが進行していることとなります。
測定方法
心エコー検査(超音波)で、心臓の短軸断面(横の断面)を撮影し、心臓が最も拡張しているときの左心房(LA)と大動脈(Ao)の大きさを比較して比率を計算します。
基準値
• 正常:LA/Ao ≦ 1.6
• 軽度拡大:1.6~2.0
• 中等度拡大:2.0~2.5
• 重度拡大:2.5以上
2. LVIDDN(体表面積正規化左室拡張末期径)(Left Ventricular Internal Diameter in Diastole (Normalized))とは
何を表す?
LVIDDNは、左心室の拡張具合を体の大きさに合わせて標準化した指標です。
まずは「体表面積正規化」は置いておいて、「左室拡張末期径」から説明します。
左室拡張末期径とは?
左室→左心室の
拡張末期→最も広がった時の
径→長さ。
つまり、「左心室が一番広がっている時の長さ」のことを指しています。
「体表面積正規化」とは
同じ場所の長さでも、チワワとゴールデンレトリバーでは大きさが全く違いますので、体重を使って均等化したものをいいます。
具体的にはLVIDDを体重の0.294乗で割ったものがLVIDDnとなります。
LVIDDN(体表面積正規化左室拡張末期径)とは
左心室が一番広がっている時の長さを体重をつかって標準化した数値
心臓は血液がたくさん入ってくると、頑張ってたくさん広がろうとします。
心臓がたくさん広がっている→心臓が頑張りすぎている
ということになります。
LVIDDnを一言で説明するのであれば
左心室が拡大していないかを確認するための数値、心臓が頑張りすぎていないか確認するための数値ということになります。
測定方法
心エコー検査で、心臓の短軸断面を測定し、左心室の拡張末期(血液が最も溜まった状態)の内径(LVIDd)を記録します。
この値を犬の体の大きさに応じて補正し、LVIDDNとして表します。
基準値
• 正常:LVIDDN ≦ 1.7
• 軽度拡大:1.7~2.0
• 中等度拡大:2.0~2.5
• 重度拡大:2.5以上
3. VHS(椎骨心臓サイズ)
何を表す?
VHS(椎骨心スコア)(Vertebral Heart Score)は、レントゲン(X線)を使って心臓の大きさを評価する方法です。
背骨は余程のことがない限り大きさは変わりませんが、心臓は筋肉のため負担がかかると大きくなってゆきます。
一般論として大きくなると良いイメージがありますが、ゴムを伸ばしたような状態になるため
大きさが大きくなると収縮する力は弱まってしまいます。
ですので背骨(椎骨)を定規にして、左心房がどれくらい大きくなっているかを数値化するものです。
測定方法
レントゲン画像の側面像(横から見た画像)を使って、以下の2つの長さを測ります。
1. 縦軸(長軸):心臓の最も長い部分
2. 横軸(短軸):心臓の最も幅が広い部分
この2つの長さを背骨の椎骨(T4から後ろ)に重ねて、何個分の長さになるかを数値化します。
基準値
• 正常:VHS ≦ 10.5
• 軽度拡大:10.5~11.5
• 中等度拡大:11.5~12.5
• 重度拡大:12.5以上
一般的にはVHSはこれらの基準に当てはまりますが、ワンちゃんには胴長の動物やすらっとした体型の動物などがいます。
近年では品種によってVHSの正常値が異なることが明らかにされています。
なぜこれらの指標が重要なのか?
MMVDが進行すると、心臓に負担がかかり、最終的には心不全に至ることがあります。
以下のような症状が現れる場合、心臓の負担が大きくなっている可能性があります。
✅ 咳が増えた(特に夜間や興奮時)
✅ 運動を嫌がる(疲れやすい)
✅ 呼吸が荒くなる(呼吸数が増える)
✅ 失神することがある
これらの症状が見られる場合、心臓の状態を詳しく検査し、適切な治療を行うことが重要です。
まとめ
MMVDの進行を評価するために、
✔ LA/Ao(左心房の拡大具合)
✔ LVIDDN(左心室の拡大具合)
✔ VHS(X線での心臓サイズ)
が重要な指標になります。
これらの検査結果を基に、病気の進行度に合わせた治療(投薬・生活管理)を行うことが、
ワンちゃんの健康を守るために大切です。
気になる症状がある場合は、早めにご相談ください!
犬の僧帽弁閉鎖不全症(MMVD)のACVIMステージ分類と治療開始のタイミングについて
僧帽弁閉鎖不全症(MMVD)は、犬の心臓病の中で最も一般的な疾患のひとつです。
その進行度を評価し、適切な治療を行うために、ACVIM(米国獣医内科学会)は以下のようにステージ分類を行っています。
ACVIMステージ分類
• ステージA:現時点で心臓に異常はないが、将来的にMMVDを発症するリスクが高い犬種(例:キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルなど)。つまり、キャバリアちゃんはキャバリアちゃんであるという理由だけで将来的に心臓病を発症するリスクが高いとされているのです。
• ステージB:心雑音が確認されるが、臨床症状はない状態。
• B1:心雑音はあるが、心拡大が認められない。
診察の時に獣医師から「心雑音がありますね。」と言われて時点でここに入ることになります。
ですが心雑音を聴取した時に毎回お伝えしている通り「心臓に雑音がある=治療が必要」というわけではありません。
• B2:心雑音があり、心拡大が認められる。
• ステージC:過去または現在に心不全の症状(咳、呼吸困難など)があり、治療が必要な状態。
• ステージD:標準的な治療に反応しない、末期の心不全状態。
治療開始のタイミング
先ほどお伝えした通り、 「心臓に雑音がある=治療が必要」というわけではありません。治療を開始するのは一般的にはステージB2からとなります。
ステージB2:心雑音と心拡大が確認されるが、臨床症状がない段階です。
この段階で、ピモベンダンなどの強心薬の投与が推奨されます。
• ステージC:心不全の症状が現れた段階です。強心薬に加えて、利尿剤や血管拡張薬の使用が一般的です。
これらの治療は、病気の進行を遅らせ、犬の生活の質を維持するために重要です。
早期発見と適切な治療が、愛犬の健康を守る鍵となります。
犬の僧帽弁閉鎖不全症(MMVD)のACVIMステージDについて
僧帽弁閉鎖不全症(MMVD)は、犬の心臓病の中でも特に一般的な疾患で、その進行度合いに応じてACVIM(米国獣医内科学会)はステージAからDまでの分類を行っています。その中で、ステージDは最も進行した段階を示します。
ステージDの定義
ステージDは、標準的な内科治療に反応しない、進行した心不全の状態を指します。
この段階では、通常の治療法では症状のコントロールが難しく、難治性心不全とも呼ばれます。
ステージDの特徴
• 症状の持続または悪化: 高用量の利尿剤、強心剤、降圧剤などを使用しても、症状が持続するか、さらに悪化することがあります。
• 頻繁な入院: 重度の肺水腫や呼吸困難などの急性症状が再発し、頻繁に入院治療が必要となる場合があります。
• 生活の質の低下: 持続的な症状により、犬の生活の質(QOL)が著しく低下することがあります。
治療のアプローチ
ステージDの犬に対しては、以下のような高度な治療戦略が検討されます:
• 薬物療法の強化: 利尿剤や強心剤の投与量を増やす、または新しい薬剤の併用を検討します。
• 酸素療法: 呼吸困難がある場合、酸素室での治療が行われることがあります。
• 外科的治療: 内科的治療で効果が得られない場合、僧帽弁の外科的修復や置換手術が検討されることがあります。
• 緩和ケア: 症状の緩和と生活の質の向上を目的としたケアが行われることがあります。
ステージDは非常に重篤な状態であり、治療の選択肢や予後について、担当の獣医師と十分に相談することが重要です。
愛犬の生活の質を最優先に考え、最適なケアを提供するためのサポートを受けることをお勧めします。